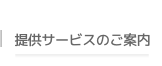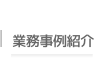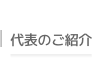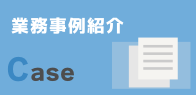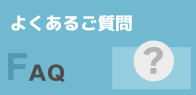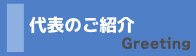業務事例紹介

業務事例紹介
Cace1.合弁会社
| 概況 | 設立から2年間で資本金が足りなくなり、増資が強要され不審になり調査を開始 そこから問題が発覚した |
|---|---|
| 手法 | 設立当初より資本金目当ての合弁であった。具体的な手法は、 1)売上の隠匿 2)固定資産の購入について関連会社を利用 3) 費用の過大計上 |
| 対策 | 1)設立より予算の作成を断行する 2)金額の支出について一定のルールを設ける 3)定期的に外部監査を導入する 4)本業以外の事業に手を出したため、うまい話に乗ってしまった。 撤退し、本業に戻る。 |
Case2.税務調査対応
| 概況 | 税務局より従来未課税の取引について課税するように言われ、千万元の影響が生じる試算となった。 |
|---|---|
| 問題 | 税法の明文のない箇所に関する指摘で、根拠と合理性に欠けるものだった |
| 対策 | 2年以上に渡る法律に基づく説明、説得、論争、攻防の結果、不課税となった。 |
Case3.単独生産会社
| 概況 | 中国生産子会社が規模の拡大とともに管理が困難になった |
|---|---|
| 問題 | 設立から10年、生産が順調に進んでいるが、規模の拡大とともに管理が困難 1)年間の損益の予測ができない 2)年間の資金繰りが分からない 3)本社の戦略を工場の実務に反映できない |
| 対策 | 1)予算制度の確立 2)資金繰り予測の確立 3)連結パッケージの導入 4)本社の戦略が迅速に工場へ伝わり、実務に即した内部システムの構築を行う |
Case4.DD調査
| 概況 | 下請け工場への出資を検討 |
|---|---|
| 問題 | 帳簿の真偽、水分の程度、出資単価の算出が必要 |
| 対策 | 前後一ヶ月の作業で、出資稟議資料が完成。5年以上安定経営中。 |
Case5.戦略会計
| 概況 | 中国子会社の管理には、戦略会計が必要である。 |
|---|---|
| 問題 | 戦略のないまま、運営をすると、 人民元高、労務費用増、原価の高騰、移転価額税制、従業員の管理、 管理者の評価などの問題に直面してしまう。 |
| 対策 | 本社の戦略を反映した、予算制度の確立、見積方式の確立、 内部管理規定の構築、評価方式の策定を行う。 |
Case6.内部統制支援
| 概況 | 世界の潮流として、上場企業の内部統制に対して、 監査人が意見を述べる方向で進んでいる(日本におけるJSOX法等)。 そのためには、まず中国子会社の内部統制システムの構築と 内部監査を実施する必要性がある。 |
|---|---|
| 問題 | 中国では内部統制に慣れていなく、人が人を管理する傾向が強い。 また、中国では日本と異なりアルバイトや副業収入を得ている人は 80%以上との調査もあり、日常の管理あるいは 内部統制システムの構築に際しても、判断の難しい問題が多い。 |
| 対策 | 内部統制システムの構築及び運用の徹底。 詳細な内部監査の実施により、事故の発生を事前に防ぐ。 |
Case7.独資子会社財務支援
| 概況 | 中国に進出する子会社の総経理に通常、営業系あるいは 技術系の総経理を派遣し、経理担当者を派遣することが困難である。 |
|---|---|
| 問題 | 子会社の総経理をサポートする経理財務スタッフが欠如し、 本来の業務以外の業務に貴重な時間を使わざるを得ない。 ▼日本本社仕様の予算の作成 ▼中国仕様の財務諸表より、日本本社仕様の予実管理資料の作成 ▼連結向けパッケージの作成 ▼中国法定監査の対応 日本本社の経理担当は必ずしも中国仕様の財務諸表を 細かく理解できるわけではないため、 連結財務諸表に重大な虚偽表示が生じうる。 |
| 対策 | 中国仕様の財務諸表を日本仕様に合わせてシステム構築し、 普段から日本本社と同じ勘定科目で運営できるようにサポートする。 予算の作成から連結パッケージの作成まで、一貫したサポートを行うことにより、 総経理が本業に集中できるようなサポートを実施。 |